
十二世市川団十郎さんが亡くなりました。十八世中村勘三郎さんに続いてのことで、残念で惜しいことです。
団十郎さんは、博多座公演のとき、船乗込みで同じ船でした。菊五郎さんも同じ船で、貴重な思い出になりました。パーティーにも呼ばれたんですが話す機会がなくて。
勘三郎さんには、もう35年ほど前でしょうか、新宿のスナックでお会いしました。偶然隣りに腰掛けたんです。
「博多っ子純情、読んでます。フアンです」といわれました。ずいぶん後、博多座出演のとき、オークラのラウンジでお見かけしたので、挨拶に行きました。「四谷怪談」のときで、勘三郎さんのお岩が毒を飲もうとしたとき、客席から中年女性の声で、「飲まんとよ~」と声がかかりました。私も観劇していたので、聞こえましたかと尋ねたら、「聞こえたけれど、飲まないわけにはいきませんからねえ」と、微苦笑されました。
初代勘三郎が建てた中村座は江戸で一番古い芝居小屋でした。音さんが東京デビューしたのは、この中村座でした。
九世は「劇聖」といわれます。明治36年に茅ヶ崎の別荘で他界しました。音さんは二度目の海外巡業のあと、敬愛する団十郎と同じ茅ヶ崎に、貞奴の名義で三千坪の敷地を求め、別荘を建てました。
伊藤博文の別荘が隣の大磯にあって、しばしば遊びに来たそうです。「萬松園」という家の名も伊藤博文がつけました。今は、敷地の一部が茅ヶ崎市美術館になっています。館長さんはそうしたいきさつを知って、たちまち「音貞病」にかかり、茅ヶ崎市民にも伝染させています。
九世が亡くなった日は、十世市村家橘が十五世市村羽左衛門に改名するので、大森海岸の料理屋に、新聞の劇評家を15人か20人招いていました。当時、歌舞伎役者の昇進や改名の際には、劇評家を料理屋に招待してお披露目する習慣だったのです。
羽左衛門が遅れてやっと顔を見せたと思ったら、「堀越さん*がとうとう亡くなってしまった」といい、茅ヶ崎へ行かなければならないのでと言って、中座しました。
残された劇評家たちは、芝居をやったり歌ったりして、宴会を続けたといいます。誰も茅ヶ崎へは行かなかったのでした。
その日、音二郎は座員たちと、弔問客のために駅から数キロの道を整備し、道しるべや外灯を立て、車をあちこちから集める手配をしたそうです。
それから、伊藤博文に弔辞を頼み、文案は依田学海**に代筆してもらいました。葬儀では音二郎がその弔辞を代読しました。
政治家の第一人者が俳優に弔辞を贈ったのは初めてでしょう。
*堀越…本名。市川は芸名。屋号は成田屋
**漢学者・演劇評論家・劇作家。川上音二郎のために『拾遺後日連枝楠』(しゅうい・ごじつの・れんし・くすのくき)を書いた。
【資料】
「団菊以後」伊原青々園・青蛙房
「博多川上音二郎」江頭光・西日本新聞社
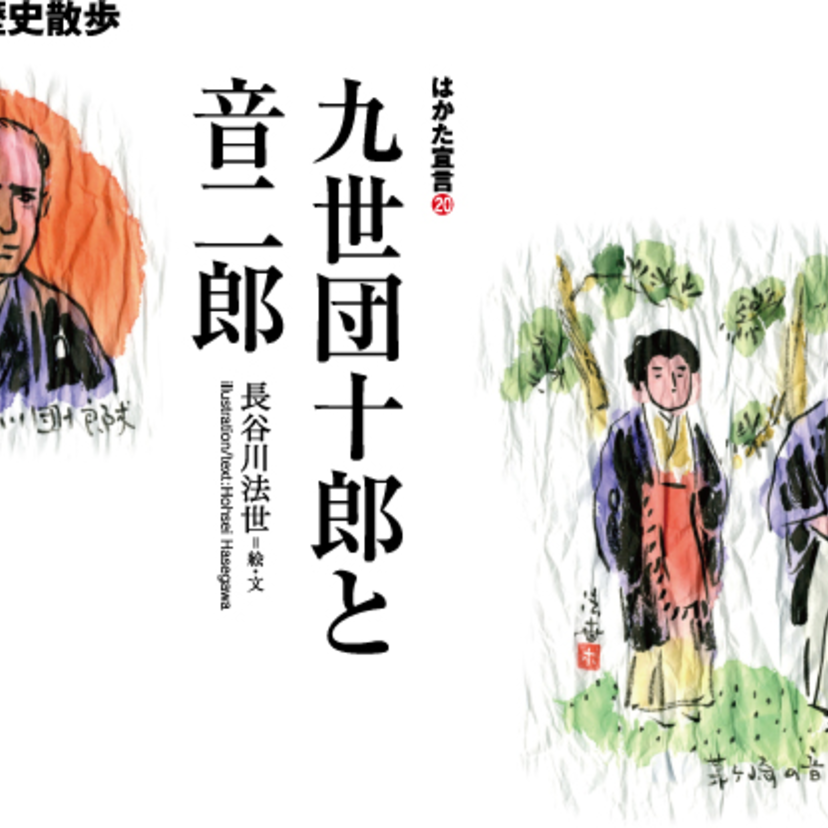
![[2025年版]50代に似合うおすすめのリップ11選|美しくみせる口紅の色選びも解説](/uploads/article/image/1919/thumb_lg_AdobeStock_285763275.jpg)
![[2025年版]退職する側から贈るプレゼントおすすめ20選|食べ物・飲み物・プチギフトなど](/uploads/article/image/772/thumb_lg_AdobeStock_240886640__1_.jpeg)
![[9歳~10歳]男の子への誕生日プレゼント14選|小学4年生が喜ぶ商品を厳選](/uploads/article/image/1321/thumb_lg_AdobeStock_357717342.jpg)
![[2025年版]中学生女子にプレゼントしたい今どきのかわいい文房具おすすめ10選。勉強も楽しくなるギフト!](/uploads/article/image/1069/thumb_lg_AdobeStock_273130714.jpg)








