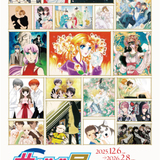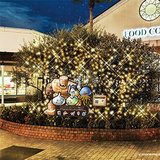まもなく訪れる海苔の旬「新海苔」の季節
一年中当たり前のように食べている海苔ですが、野菜や果物、魚のように、実は海苔にも旬の時期というものがあります。
海苔は海水の温度が18度以下にならないと育ちません。 海苔にとって、いちばん育ちやすい海水の温度は約11~13度です。海水の温度が10度より冷たくなると、海苔の成長は止まってしまいます。
産地によっても異なりますが、養殖した海苔が収穫されるのは、海水温が下がる11月初旬から4月初旬まで。一般的にこの時期が海苔の旬とされています。
養殖海苔は海苔網を海に張って、生育したものを繰り返し収穫していきます。なかでも、その網でいちばん最初に摘みとった海苔を「新海苔(初海苔、初摘み、一番摘み)」といいます。
新海苔は、全体の生産量の10%ほどしかない貴重な海苔で、高級品として主に進物に用いられています。香り高くパリッとした食感やサクッとした歯切れの良さ、口どけの良さが特徴です。
海苔網を新しいものに張り替えることで、シーズン内に何度か新海苔を収穫することもできますが、一般的には、新海苔の後、二番摘み、三番摘みと収穫が繰り返され、少しずつ硬くなり風味も変化していきます。
海の恵みがギュッと凝縮 海苔は栄養の宝庫
海苔は「海の野菜」と言われるほど、ビタミン、ミネラルなど、さまざまな栄養をバランスよく含んでいます。
また、3~4割が良質なタンパク質で構成されており、「畑の肉」大豆のように、海苔は「海の肉」といわれています。
消化を助ける酵素や食物繊維も豊富で、そのうち、海苔だけに含まれる水溶性食物繊維であるポルフィランは、血中のコレステロールを下げたり、腸内環境を整えたりする効果があるといわれています。
さらに、赤血球の合成に大きく関わり、貧血を防ぐ効果がある葉酸は、100gあたりの含有量でみれば、鶏レバーと並んでトップクラスです。
このように、豊富な栄養素を含む海苔への関心は、最近の日本食ブームとともに海外でも高まり、以前は”ブラックペーパー“と呼ばれ敬遠されていた海苔も、今では多くの国で食べられるようになりました。
栄養成分表(100gあたりの含有量)

※全型焼き海苔は1枚約3g ※Tr:ごく微量
出典:日本食品標準成分表(八訂)増補2023年
おいしさの秘密は 奇跡の三大うまみ成分
海苔には、日本の伝統的な三大うまみ成分「グルタミン酸」、「イノシン酸」、「グアニル酸」が含まれており、これらのうまみをすべて含むのは、天然食品の中では、唯一といわれています。
昆布のうまみ成分・グルタミン酸は、タンパク質を構成するアミノ酸の一つで、料理にまろやかでコクのあるおいしさを作り出します。鰹節や煮干しのうまみ成分・イノシン酸、干し椎茸のうまみ成分・グアニル酸は核酸の一種で、単独でもうまみがありますが、グルタミン酸と組み合わせると”うまみの相乗効果“が働き、より強力なうまみを生み出すのが特徴です。

海苔にはこれらの成分量が多いばかりでなく、それぞれのバランスが良いため、自然の力で驚異のおいしさを作り上げているのです。
身近すぎて知らなかった! 海苔の豆知識
■海苔はいつから食べられていたの?
飛鳥時代に制定された「大宝律令」によれば、29種類の海産物が租税として納められており、海苔がその1つとして表記されています。現在のような乾燥した海苔ではなく、生海苔が一般的でした。平安・鎌倉時代でも貴族に珍重され、江戸時代に入って養殖技術が発達し、現在の板海苔の原型が完成。江戸の特産物として扱われていましたが、海苔の生態は明らかにされておらず生産量は不安定でした。やがて昭和に入ると、イギリスの海藻学者・ドゥルーが海苔の生態を解明し、一気に養殖技術が全国に普及しました。
■海苔の原料はどんな海藻?
海藻は、含まれる色素によって紅藻類、緑藻類、褐藻類の3つに分けられます。私たち日本人が普段食べる板海苔の原料となるのは紅藻類のアマノリ属に属する海藻で、主に「スサビノリ」と「アサクサノリ」の2種類です。スサビノリは、日本で最も一般的な海苔原料です。アサクサノリは主に関東地方で養殖され、1945年頃まで養殖海苔の主流の品種でしたが養殖が難しく、現在は絶滅危惧種に指定されています。ちなみに、青海苔の原料となるアオサは緑藻類、昆布やワカメ、ヒジキは褐藻類です。
■最も多く海苔を食べる国はどこ?
古くから海苔を食用としてきた国は、日本、中国、韓国、イギリス(ウェールズ地方など一部地域)の4カ国です。イギリスでは形状が異なりペースト状の岩海苔が一般的です。世界の養殖生産量(生海苔ベース)は101万トンで、韓国が全体の55.1%を占め、日本23.0%、中国21.6%と続きます。世界で最も海苔を消費しているのは韓国で、国民1人当たりの年間消費量が140枚以上と、日本(約80枚)の1.5倍以上です。
※1枚=全型/縦21cm×横19cm
参考:日本応用藻類学会誌
■実は似て全く非なるもの!? 日本の海苔と韓国海苔
塩とゴマ油などで味付けされ、薄くてサクサクと歯切れがよいのが特徴の韓国海苔。日本の海苔とは原料となる海藻が異なり、日本では岩海苔として知られるオニアマノリやイチマツノリなどの海藻が使われています。岩海苔はすいた際に穴が開きやすいため、日本では主に加工品に使われます。日本では薄いスサビノリを細かく刻んで均等な厚さに仕上げるのに対し、韓国では厚みのある岩海苔を適度な大きさを残して成形します。 そのため、濃淡のある仕上がりになり、高級品ほど薄くたくさんの穴が開いています。
■最近人気急上昇中の「バラ海苔」とは?
収穫した海苔の原藻(げんそう)を板状に成形せず、ばらばらの状態で乾燥・焼き上げた海苔。ミンチ機(破砕機)にかけないので、うまみ成分や栄養成分が流出しにくく、ふわっとした食感と歯触りで海苔本来の風味が楽しめます。繊維質も柔らかいため、小さなお子様や高齢者も食べやすく、味噌汁やうどん、サラダなどにそのまま振りかけられる手軽さがウケています。

協力/全国漁連のり事業推進協議会

![[2025年版]退職する側から贈るプレゼントおすすめ20選|食べ物・飲み物・プチギフトなど](/uploads/article/image/772/thumb_lg_AdobeStock_240886640__1_.jpeg)
![[2025年版]50代に似合うおすすめのリップ11選|美しくみせる口紅の色選びも解説](/uploads/article/image/1919/thumb_lg_AdobeStock_285763275.jpg)
![[9歳~10歳]男の子への誕生日プレゼント14選|小学4年生が喜ぶ商品を厳選](/uploads/article/image/1321/thumb_lg_AdobeStock_357717342.jpg)
![[2025年版]50代におすすめの導入美容液12選|エイジングケアに効果的なブースター美容液の選び方](/uploads/article/image/1886/thumb_lg_AdobeStock_652638480.jpg)
![[2025年版]中学生女子にプレゼントしたい今どきのかわいい文房具おすすめ10選。勉強も楽しくなるギフト!](/uploads/article/image/1069/thumb_lg_AdobeStock_273130714.jpg)