
旧年中は音二郎さんの生誕150年でお世話になりました。本年も博多と音さんをよろしくお願い申し上げます。
お正月。初詣から年中行事のはじまり。「博多カレンダー」*1 を見ると元旦初詣から3日筥崎宮玉せせり・沖濱恵比須例大祭、7日鏡天満宮新春大祭、8日から十日恵比須神社大祭、11日承天寺宝賽式、13日 田神社鏡開き、16日海元寺閻魔祭、19日恵比須流恵比須講、20日恵比須堂二十日恵比須大祭、23日葛城将軍地蔵尊大祭、24日博多松囃子振興会初寄り、28日は不動明王大祭、千代流れ玉手箱引継式、そして本年最初の博多祗園山笠振興会総会と、せまい博多のあちらこちらで行事の花ざかりです。ちなみに2月1日は博多町家ふるさと館の博多餅つきです。
日本民俗学の大先達柳田国男さんは「ハレ」と「ケ」の循環の中に日本人の生活のリズムがある、とおっしゃっていたようですが、もし博多の行事一覧をご覧になっていたら、きっと自説を変更されたことでしょう。博多の生活リズムは「ハレ・ハレ・ハレ…ときどきケ」の循環である、とかなんとか。
年中行事の語源*2は、平安時代宮中で年々恒例の行事を忘れぬように示した表のことでした。表とは帝の常の御所である清涼殿に置かれた「年中行事御障子文」という宮廷カレンダーなんですね。みんなで確認するように、つい立の障子に書かれていました。仁和元年(885)に太政大臣藤原基経がはじめて献上したそうです。
後白河院の時代、1170年代には「年中行事絵巻」60巻が製作されました。これは模本が17巻現存していて、その複製本は去年「徒然草」を漫画化したとき、参考書として大いに活用しました。
宮廷の政治は「政=祭り事」といわれ、実は年中行事をつつがなく消化していくこと、だったらしいんです。祭政一致の時代ですから神仏に国家安泰を祈願する事などが主要な政でした。国家の体制がかたまれば、年中行事もととのい、その催行だけで平和な時代がつづきます。
時代が移り、国の舵取りが貴族から武家に移行すると、年中行事も武家用になって行きます。その鎌倉以来の軍事政権が、ようやく明治維新で王政復古。それから戦後は民主主義となりました。
年中行事絵巻と博多カレンダーを見比べると、平安時代の貴族の行事がすこしずつかたちをかえて市民のものとなっていることがわかります。
*1 博多カレンダー…博多の年中行事が満載のカレンダー。写真を見るだけでも楽しい。櫛田神社他で販売する
*2 年中行事の語源…百科事典マイペディアによる
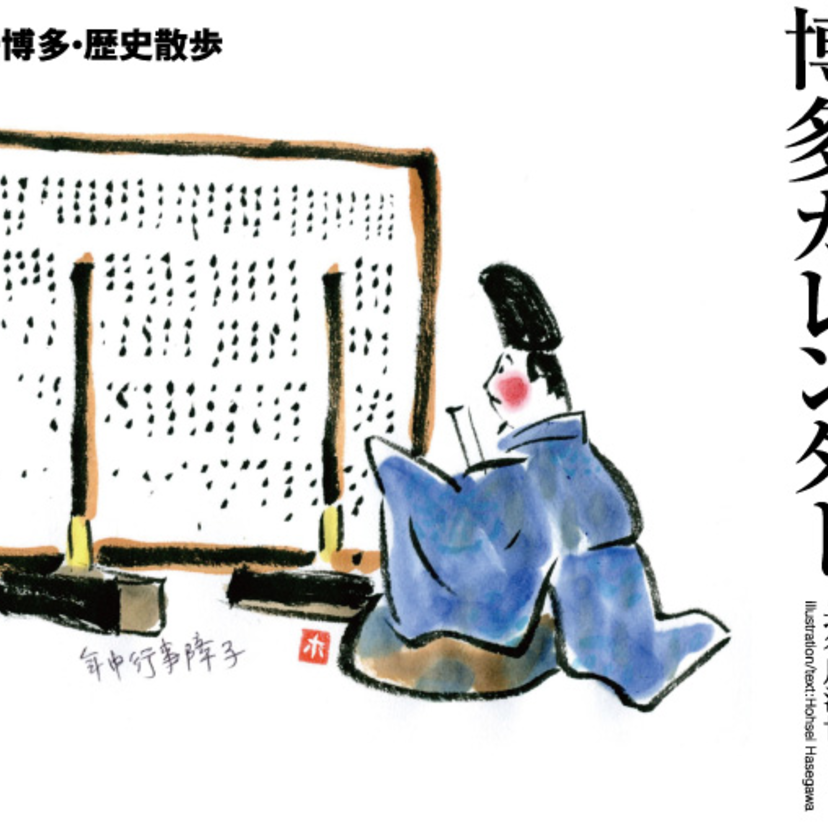
![[2025年版]50代に似合うおすすめのリップ11選|美しくみせる口紅の色選びも解説](/uploads/article/image/1919/thumb_lg_AdobeStock_285763275.jpg)
![[2025年版]退職する側から贈るプレゼントおすすめ20選|食べ物・飲み物・プチギフトなど](/uploads/article/image/772/thumb_lg_AdobeStock_240886640__1_.jpeg)
![[9歳~10歳]男の子への誕生日プレゼント14選|小学4年生が喜ぶ商品を厳選](/uploads/article/image/1321/thumb_lg_AdobeStock_357717342.jpg)
![[2025年版]中学生女子にプレゼントしたい今どきのかわいい文房具おすすめ10選。勉強も楽しくなるギフト!](/uploads/article/image/1069/thumb_lg_AdobeStock_273130714.jpg)








