
承天寺に建つ川上音二郎さんの墓石の話。緑がかった自然石で見上げるばかり。あれは何という石だろう。
「ノギタイシていうとですたい」
博多の石屋さんが教えてくれた。
「糸島に野北がありまっしょうが」
「ああ、野北牧場の」
いまは野北海岸のほうがとおりがいいようだ。以前は野北馬の放牧場がピクニックの定番だった。はじめての野北牧場は、高1の美術部遠足。先輩からキング・ワンというゲームを教わった。高三のときには体育祭打ち上げのグループ遠足 *1。はじめて馬に乗った。ところが馬に嫌われてしまって。あぶみに片足かけたら、牧童さんが手綱を押さえているのに、首をねじ曲げて足に噛みつこうとするんだもの。どうにか跨るといきなり後ろ足で竿立ちになる。まうしろに飛び降り、すぐ横っ飛びして逃げた。中一のとき体操部に入っていたのが役にたった。それにしても野北の馬は相性 *2が悪かった。
野北石の話。野北はもともと岩山で、その海岸べりは岩が露出している。地学的には結晶片岩というらしい。著しい剥離性片状構造、つまり、平板状によく剥がれる性質。そう聞くと芥屋の大門をすぐに思い浮かべるが、あちらは玄武岩で多角形の柱状列石。ひらべったくないので石碑には不向きだそうな。
さて、石屋さんは岩の崖にくさびを打ち込んで崖から大きな板状に石を剥がす。石は海に落ちる。石屋さんは海中の石の形や大きさや位置、それから落とした日時を記した海中地図をつくる。地権というか石権というかちゃんと権利があって、石を海中に貯蔵するのだ。石は年月をかけて波にうたれ洗われて、なめらかになっていく。それでようやく文字を刻みやすくなる。
石の注文があると、地図をお客さんに見せる。形・大きさ・値段などを相談し、話がまとまると海から引き上げる。
「盗まれたりしないんですか」
笑われた。海から引き上げるのは大変な作業なのですぐ発覚する。泥棒はいないということだ。
音さんの墓石は破天荒な生涯そのままの桁違いの大きさだ。浜に引き上げるだけでも大変な作業だったろう。船か筏に吊り下げて運ぶと聞いたように記憶する。陸揚げしたあと工場で形を整え、文字を刻み、お墓や記念碑 *3として完成させる。
だけれど、いまでは輸入外国産の御影石や大理石のほうが安い。費用と時間がケタ違いの野北石の注文はまったくないらしい。だから野北の崖下の海中にはいくつもの石があり、ずいぶん丸っこくなりながら人知れず波に打たれているのだ。逝きし世の面影 *4をみる思いがする。
*1)グループ遠足…Dグループの一、二、三年生。東京オリンピックの前年1963年。青春の思い出はもはや半世紀前。負けあせんぞ?!
*2)(馬との)相性…30年後に阿蘇の草千里で幼稚園の息子と馬に相乗りしたら、これがむずとも動かなくって。
*3)記念碑…音次郎誕生碑の建つ沖浜稲荷神社の境内には戦災地蔵があり、何の記念碑か寄付金額や氏名を彫った野北石が台座のあいだに敷かれている。空襲のためだろうか割れている。
*4)「逝きし世の面影」…渡辺京二著(平凡社ライブラリー)。幕末明治の来日外国人の記録をもとにした日本文明論の名著。
◎お知らせ…11月11日(火)は音二郎忌。承天寺で10時より法要。どなたでもどうぞ。
博多町家ふるさと館では「消えた音二郎君の銅像展」を開催。11月1日(土)~30日(日)
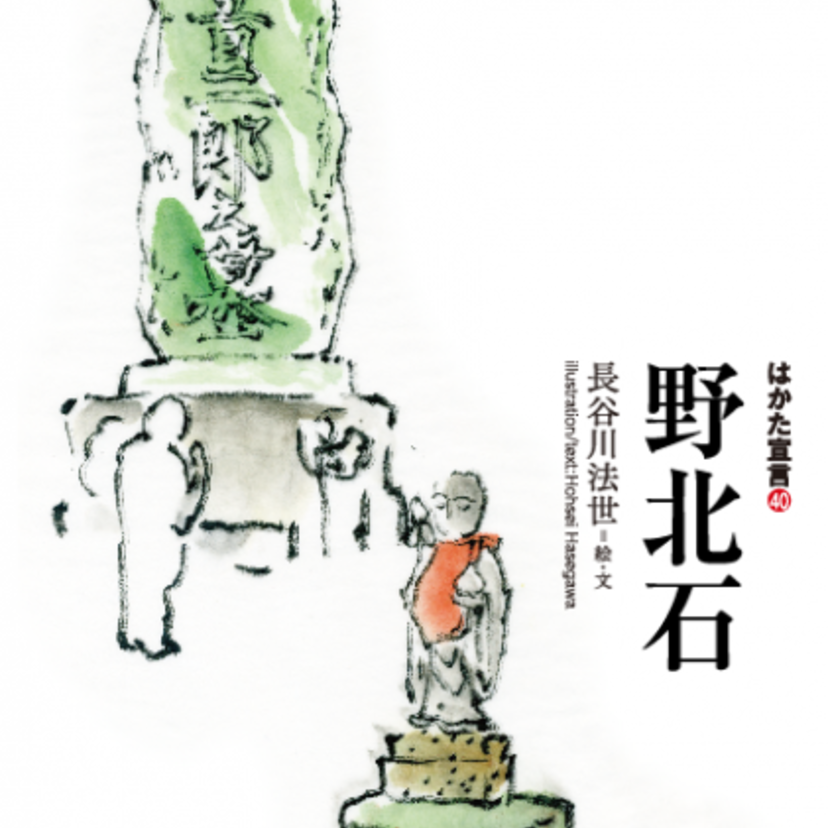
![[2025年版]50代に似合うおすすめのリップ11選|美しくみせる口紅の色選びも解説](/uploads/article/image/1919/thumb_lg_AdobeStock_285763275.jpg)
![[2025年版]退職する側から贈るプレゼントおすすめ20選|食べ物・飲み物・プチギフトなど](/uploads/article/image/772/thumb_lg_AdobeStock_240886640__1_.jpeg)
![[2025年版]中学生女子にプレゼントしたい今どきのかわいい文房具おすすめ10選。勉強も楽しくなるギフト!](/uploads/article/image/1069/thumb_lg_AdobeStock_273130714.jpg)
![[9歳~10歳]男の子への誕生日プレゼント14選|小学4年生が喜ぶ商品を厳選](/uploads/article/image/1321/thumb_lg_AdobeStock_357717342.jpg)







