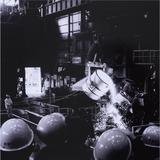白玉の歯にしみとおる秋の夜の 酒はしづかに飲むべかりけり 若山牧水
さて、『日本語全史※1』(以下、全史)は、題名どおり日本語の歴史を書いた本だ。万葉集でつかわれている古いことばが、現代語になるまでの、移り変わりが書いてある。
印象深いのは、日本語の歴史は日本史とおなじであるということ。言葉のひとつひとつに栄枯盛衰があって、人間ドラマとすこしもかわらない。スリルとサスペンスに満ちた超大河ドラマなんだな。
例えば、願望の助動詞「まほし※2」ということばは、院政時代にはつかわれなくなって、かわりに「たし」が登場した(例:酒は飲みたし金は無し)。その新興勢力も時代とともに連体形「たき」のイ音便「たい」の形となって(酒は飲みたい金は無い)継承されたのだとか(全史228頁)。なにやら、源頼朝の鎌倉幕府がいつのまにか、北条政権あるいは足利政権へと変態を繰りかえしたのに似ている。
さて、「たし」ということばを、藤原定家は「俗人の語」だから和歌にはつかわないといっているそうだ。その「たし」の語源は形容詞「いたし」だろうという。用例として全史はなんと九州※3の遊行女婦児島の和歌※4を紹介している。
凡ならばかもかもせむを畏みと振り痛き袖を忍びてあるかも(万葉集965)
〈普通であればどのようにでもしようが、畏れ多いと思って振りたい袖を耐え忍んでいることよ〉(全史:229頁)
天平2年(730)大宰府長官であった大伴旅人が大納言となって都にのぼるときの送別の歌だ。旅人が水城で振り返ると、見送りの人々のなかに児島がいた。その時の児島の歌二種※5の一つが右の万葉集965なのだ。
「振り痛き袖」だけれど、太宰府市の万葉歌碑15号碑※6には「振りいたき」と彫られており、説明板の読みも同じだ。万葉集原文は「振痛袖」で、「振りいたき袖」と読むのだろうが、「振りたき袖」と読むネット記事もおおい。けれど、奈良時代の筑紫方言なのは確かだ。「痛き」は「いたし」の連体形で、「たし」に変化し、この筑紫方言が中央語になっていったのかもと全史がいうのはヤッターだ。
いずれにしろ博多では、「振り痛き」は「振り痛か」に変貌し、「いたか」は願望「たか」となって継承され、現代においては「酒は飲みたか金は無か」と、無い袖を忍びてあるかも、なのであ~る。
※1)日本語全史…沖森卓也著。ちくま新書
※2)まほし…「あらまほし」などと使う
※3)九州…万葉集原文は「筑紫」。遊行女婦の文献初出が児島らしい。
※4)児島の和歌…原文は「凡有者左毛右毛将為乎恐跡振痛袖乎忍而有香聞」
※5)歌二種…966番は「大和道は雲隠りたりしかれども我が振る袖をなめしと思ふな」。旅人の歌二種:967「大和道の吉備の児島を過ぎて行かば筑紫の児島思ほえむかも」968「ますらをと思へる我れや水茎の水城の上に涙拭はむ」
※6)15号碑…ところが「太宰府市観光情報」HPの「万葉歌碑一覧」は「振りたき袖」となっている。写真は判読不能。「万葉歌碑の画像」もあるがこれも読めない。しかしマニアの近接写真ではちゃんと「振りいたし」と読める。




![[9歳~10歳]男の子への誕生日プレゼント14選|小学4年生が喜ぶ商品を厳選](/uploads/article/image/1321/thumb_lg_AdobeStock_357717342.jpg)
![[2025年版]退職する側から贈るプレゼントおすすめ20選|食べ物・飲み物・プチギフトなど](/uploads/article/image/772/thumb_lg_AdobeStock_240886640__1_.jpeg)
![[2025年版]50代に似合うおすすめのリップ11選|美しくみせる口紅の色選びも解説](/uploads/article/image/1919/thumb_lg_AdobeStock_285763275.jpg)
![[2025年版]中学生女子にプレゼントしたい今どきのかわいい文房具おすすめ10選。勉強も楽しくなるギフト!](/uploads/article/image/1069/thumb_lg_AdobeStock_273130714.jpg)