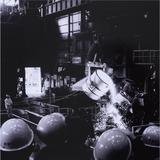桜の季節と二人の優子さん
西日本新聞ヘルスセンター(太宰府市坂本)の一角に「優子桜」が植えられたのは、2006年の初夏だった。
新聞社の診療所で保健師をしていた浜崎優子さんは、この年の3月に肝不全のため58歳で亡くなった。「ハマちゃん」「ハマさん」と親しまれ、定年後は働く女性のための保育園づくりや途上国で子供たちの栄養向上や医療改善のお手伝いをしたいと夢を語っていた。
そんな彼女を偲び、仲間たちで植えたのが「優子桜」。この季節にはいつも見事な花を咲かせてくれるが、今年の桜はこれまでと違う悲しみの中で盛りを迎えた。
今年2月、黒木優子さんが乳がんで逝った。彼女もハマちゃんと同じ享年58。西日本新聞TNC文化サークル(天神)で長く窓口に座り、受講生と講師の皆さんに愛され、仲間からは絶大な信頼を受けていた。数えきれない別離を体験してきたが、彼女との別れはどんな言葉をもっても心情を伝えられないのである。
病魔に侵された作家の中には、病床日記や随筆随想の形で闘病記を書き残した人が多い。小説家で、詩人の高見順(昭和40年、58歳で死去)は死の前年に詩集『死の淵より』を発表。また、『高見順闘病日記』(上・下)は、がんと対峙した56歳から58歳までの壮絶な闘病記録である。
高見順は神様から「時間」というプレゼントをもらい、死、生、病に渾身の筆を振るった。だが、残念ながら二人の優子さんに多くの「時間」は与えられなかった。
旧冬、黒木優子さんの入院を知った私は急いでメールを二通送ったが、律儀な彼女にもかかわらず返信が届くことはなかった。もし、彼女にも病いと緩やかに過ごせる「時間」があったなら、言い残したい、書き残したいことがいっぱいあっただろうに…。
高見の詩集『死の淵より』の中に「帰る旅」と題した詩がある。高見は死を「帰るところ」と考え、〈帰れるから/旅は楽しいのであり/旅の寂しさを楽しめるのも/わが家にいつかは戻れるからである〉と歌う。
死を「帰るところ」と考え、「土に還る」と考えるのは日本人の死生観である。高見は〈大地へ帰る死を悲しんではいけない〉とつづる。死は、土=大地=自然へと還ることなのだから決して悲しくはない、というのだ。
4月、九州では早くも花散らしの風が吹き始めた。
「ながむとて花にもいたく馴れるれば 散る別れこそかなしけれ」。西行は現世の無常迅速をこう歌っているが、花は散ってもその後には瑞々しい若葉がふき出る葉桜の季節がやってくる。浜崎さんは天草に、黒木さんは篠栗に、古里の桜花に包まれていま静かに眠っていることだろう。
(ジャーナリスト。元西日本新聞記者)
馬場周一郎=文
幸尾螢水=イラスト

![[2025年版]退職する側から贈るプレゼントおすすめ20選|食べ物・飲み物・プチギフトなど](/uploads/article/image/772/thumb_lg_AdobeStock_240886640__1_.jpeg)
![[2025年版]50代に似合うおすすめのリップ11選|美しくみせる口紅の色選びも解説](/uploads/article/image/1919/thumb_lg_AdobeStock_285763275.jpg)



![[2025年版]中学生女子にプレゼントしたい今どきのかわいい文房具おすすめ10選。勉強も楽しくなるギフト!](/uploads/article/image/1069/thumb_lg_AdobeStock_273130714.jpg)

![[9歳~10歳]男の子への誕生日プレゼント14選|小学4年生が喜ぶ商品を厳選](/uploads/article/image/1321/thumb_lg_AdobeStock_357717342.jpg)