会員になっているスポーツジムは、福岡市城南区梅林にある。その昔は梅の木が沢山あったらしいが、開発の波を受けて次第に消えていった。
過日、しだれ梅の横を歩いていると、設置された小さな掲示板で次のような和歌を見つけた。
「枯れてなお また巡り来るきさらぎに 開花のきざし翁の夢」(由良)
歌の解説もあった。「このしだれ梅たちは枯れたように見えるけど、季節がめぐり、毎年二月頃にはきれいな花を咲かせるんだよ!と、夢を語る花咲爺さんの詠(うた)です」
昨年は梅に沸いた記念すべき年だった。
「初春の令月にして、気淑(よ)く風和らぎ、梅は鏡前の粉(こ)を披(ひら)き、蘭は珮後(はいご)の香を薫らす」。令和の典拠となった万葉集の「梅花の歌」三十二首の序文だ。なんと麗しく、優美なことか。
一月下旬には九州各地で「梅の春」が始まる。ちなみに、福岡の白梅の平均開花日は2月2日。俳句の季題では、冬の梅見は探梅、春は観梅である。
探梅といえば、この季節が訪れると、私はいつも次の故事成語を口ずさむ。
「春は枝頭(しとう)に在(あ)って己(すで)に十分」(『鶴林玉露』所収の尼悟道の句)
ひねもす春を訪ねて歩き回ったが、春の気配はどこにもなかった。家に帰って、笑いながら梅の小枝をつまんで香りをかぐと、春はなんと我が家の梅の梢にいち早く訪れていた…。
私はこの言葉に強く魅かれる。これは単なる「探春」の詩ではない。春(幸福)はどんなに遠くまで探し求めても手に入れられるものではない。それよりもむしろ、身近なところにこそ存在するものだ。そのことを説く「思想詩」なのである。
「江南一枝之春(こうなんいっしのはる)」と題する詩がある。三国時代、江南(揚子江以南の温暖な地方)に住んでいた陸凱が、北方の長安に暮らす范曄(『後漢書』の作者)に「ここ江南には、なにも贈る物がないので、とりあえず梅の一枝とともに春をお届けします」と春を報じたことをいう。実に味わい深い。
「梅一輪 一輪ほどの 暖かさ」(服部嵐雪)
令和の里の白梅にも、梅林のしだれ梅にも、そんな春が忍び寄っている。
令和の里の白梅にも、梅林のしだれ梅にも、そんな春が忍び寄っている。
(ジャーナリスト。元西日本新聞記者)

馬場周一郎=文
text:Shuichiro Baba
幸尾螢水=イラスト
illustration:Keisui Koo
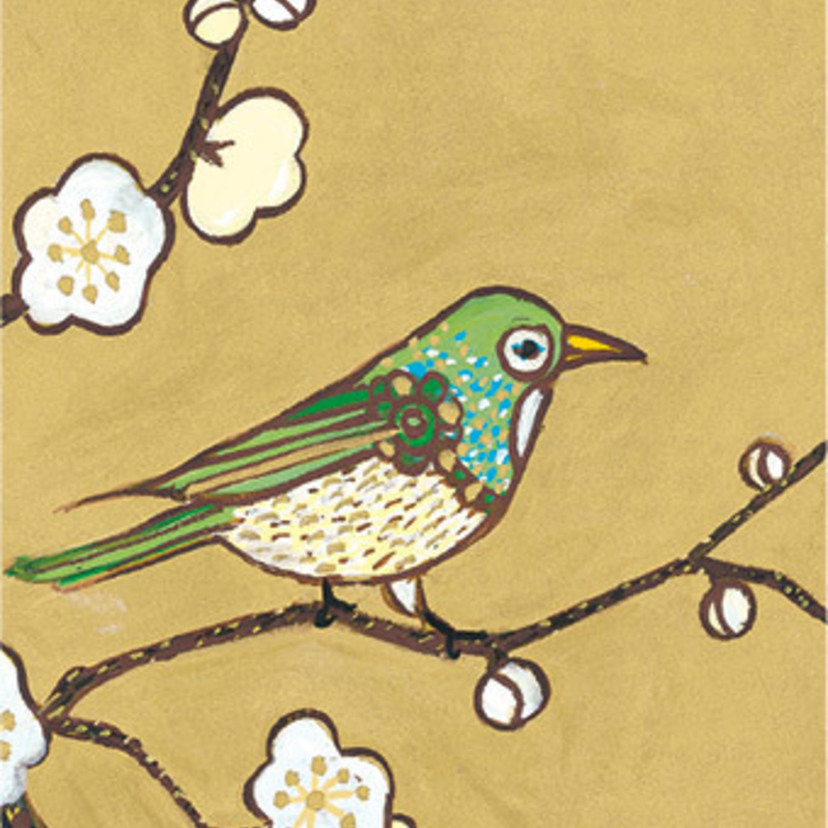
![[2025年版]退職する側から贈るプレゼントおすすめ20選|食べ物・飲み物・プチギフトなど](/uploads/article/image/772/thumb_lg_AdobeStock_240886640__1_.jpeg)
![[2025年版]50代に似合うおすすめのリップ11選|美しくみせる口紅の色選びも解説](/uploads/article/image/1919/thumb_lg_AdobeStock_285763275.jpg)
![[2025年版]中学生女子にプレゼントしたい今どきのかわいい文房具おすすめ10選。勉強も楽しくなるギフト!](/uploads/article/image/1069/thumb_lg_AdobeStock_273130714.jpg)
![[9歳~10歳]男の子への誕生日プレゼント14選|小学4年生が喜ぶ商品を厳選](/uploads/article/image/1321/thumb_lg_AdobeStock_357717342.jpg)







