
いまさらだけれど「博多」という地名について。土地が「博く」人も物も「多い」など、説はいくつもあるがどれもピンとこない。
前にも書いたが、博多についての一番古い文献は続日本記だ。大宰府古代史年表*1の現代文記事で代用する。
「天平宝字3年(759)3月24日大宰府、府官の不安四か条を言上する。その内容は(一)警固式*2によると博多大津及び壱岐・対馬等の要害の地には船一〇〇隻以上を
置き、不備に備える必要があるが、いまそれに用いる船がない(以下略)」
つまり、大宰府の官吏が防備不足の不安をうったえている。警固式というのは藤原宇合がつくった軍備計画で、九州の軍団を整備強化する役目の西海道節度使として、732年大宰府に赴任してくった。その警固式に博多大津の名称が書かれているのなら、732年より前から博多大津とよばれていたことになる。
さて、今年の高校ラグビーで東福岡高が3年ぶり5度目の全国優勝を果たした。お正月がいっそうめでたくなったが、話は対戦相手の御所実業高。その校名は所在地の奈良県御所市にちなんでいる。御所とはなじみのない地名だが、この地に「博多山」があるとなると急に親近感がわいてしまう。
博多山の名は古事記・日本書紀にでている。第五代孝昭天皇の御陵が、博多山につくられたと書いてあるのだ。「掖上博多山陵*3」という。太宰府市史編集委員・長洋一さんの「散在する博多の地名-古代」(市史だより154)という一文があって、博多山のほか、「紀氏家牒」には葛城地方(現奈良県の一部)に博多郷がみえ、「続日本紀」770年3月には、称徳天皇*4が河内国(現大阪市の一部)の博多川で曲水宴を行った。「延喜式」神名帳によると、和泉(現大阪市南部)に博多神社がみえるということだ。
また、博多大津は、古くは536年に置かれた那津宮家の「那津」であり、661年斉明天皇*5の西下のときには「那大津」ともいわれ、一時期「長津」ともよばれたそうだ。博多大津と呼ばれるのはそのあとということになる。地に歴史ありだ。
以下は古事記と日本書紀の現代訳を抜書きしたもの、為念。
古事記*6「ミマツヒコカエシネノ命は、葛城の掖上に宮殿をつくって〔今の奈良県御所市といわれる〕、天下を治めた。…この天皇は、その年九十三歳。陵は葛城の掖上の、博多の山の上にある」
日本書紀*7「観松彦香殖稲天皇〔孝昭〕…秋七月、都を掖上〔御所市池之内辺〕に遷した。これを池心の宮という。…八十三年*8、秋八月五日、天皇が崩じた。…(補 第六代孝安天皇の)三十八年*9、秋八月一四日、ミマツヒコカエシネ天皇を、掖上の博多山の上の陵に葬った」
*1)大宰府古代史年表…川添昭二監修・重松俊彦編・吉川弘文館
*2)警固式…博多の人なら「けごしき」とよむだろうが、警固は辞書で「けご」ではなく「けいご」ででる。警護と同じ
*3)掖上博多山陵…宮内庁HPの「天皇陵」では「掖上博多山上陵(わきのかみのはかたのやまのえのみささぎ)」となっている。記紀ともに原文は漢字・漢文なので読み方は種々あるようだ。
*4)称徳天皇…女帝。孝謙天皇の重祚(ちょうそ。退位した帝が再び位につくこと)
*5)斉明天皇…女帝。皇極天皇の重祚。百済救援のため西下し、筑紫の朝倉宮で没した。
*6)古事記…福永武彦訳「現代語訳古事記」河出文庫
*7)日本書紀…山田宗睦訳「原本現代訳39 日本書紀上」ニュートンプレス
*8)八十三年…孝昭天皇の在位年数。18歳から皇太子在位12年なので、113歳で崩じられたことになり、古事記の93歳と異なる。長命すぎると思われるが、当時の1年は現在の半年であったという説がある。
*9)三十八年…孝安天皇の在位38年目
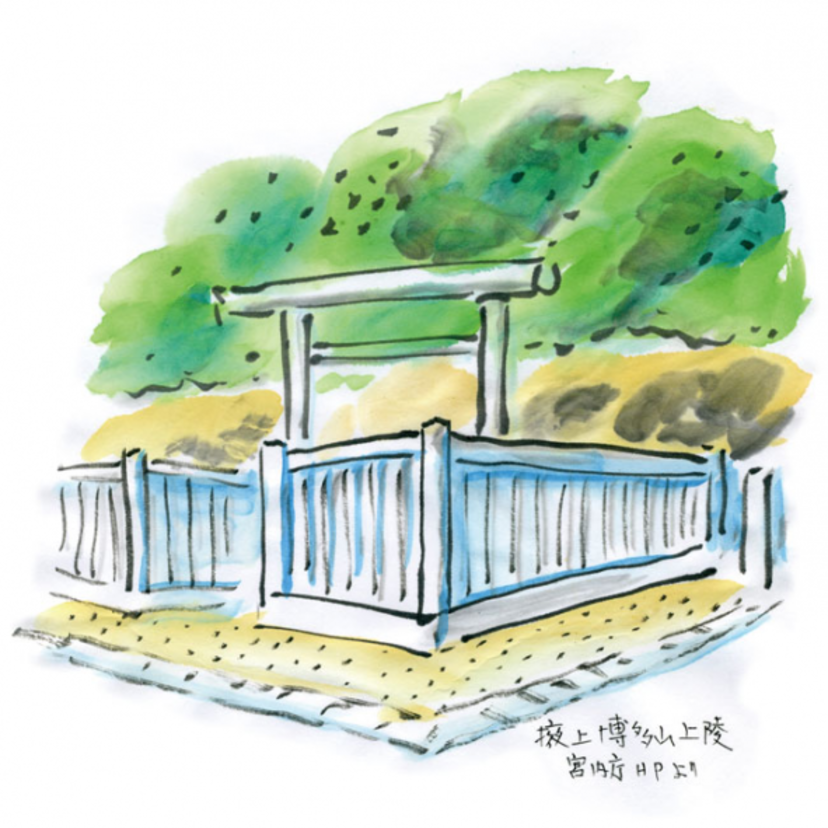

![[2025年版]50代に似合うおすすめのリップ11選|美しくみせる口紅の色選びも解説](/uploads/article/image/1919/thumb_lg_AdobeStock_285763275.jpg)
![[2025年版]退職する側から贈るプレゼントおすすめ20選|食べ物・飲み物・プチギフトなど](/uploads/article/image/772/thumb_lg_AdobeStock_240886640__1_.jpeg)
![[9歳~10歳]男の子への誕生日プレゼント14選|小学4年生が喜ぶ商品を厳選](/uploads/article/image/1321/thumb_lg_AdobeStock_357717342.jpg)



![[2025年版]中学生女子にプレゼントしたい今どきのかわいい文房具おすすめ10選。勉強も楽しくなるギフト!](/uploads/article/image/1069/thumb_lg_AdobeStock_273130714.jpg)



